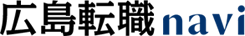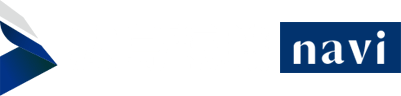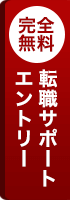転職のための広島生活情報
はじめに
日本で「ボーナス」と呼ばれる賞与は、多くの働く人々にとって大きな関心事のひとつです。給与とは別に支給されるこの賞与は、どのように始まり、どのように現在の形になったのでしょうか。また、海外と比べてどのような違いがあるのでしょうか。今回は、賞与の歴史と国際的な比較をわかりやすくご紹介します。
日本の賞与のはじまり 〜江戸時代の年礼にルーツ〜
日本の賞与の起源は江戸時代にさかのぼります。当時は「年礼」や「祝儀」として、商家の主人が年末やお正月に使用人に金品を渡す習慣がありました。これは、一年間の労をねぎらう「ごほうび」としての意味合いが強かったのです。
また、武士の世界でも、主君が家臣に褒美を与える風習がありました。こうした伝統が、現代の賞与文化の土台になっています。
また、武士の世界でも、主君が家臣に褒美を与える風習がありました。こうした伝統が、現代の賞与文化の土台になっています。
明治〜昭和:制度化と一般化の流れ
明治時代に入ると、西洋式の雇用制度の導入とともに、年末・年始に支給される金品が制度として整い始めました。昭和の高度経済成長期には、「年2回のボーナス支給」が大企業を中心に一般化し、労働組合との交渉により賞与が給与体系の一部として位置付けられるようになります。
企業の業績向上に伴い、賞与は「利益還元」の色合いを強め、社員のモチベーションや忠誠心の向上を目的とする制度へと発展していきました。
企業の業績向上に伴い、賞与は「利益還元」の色合いを強め、社員のモチベーションや忠誠心の向上を目的とする制度へと発展していきました。
現代の賞与制度の特徴
現在の日本企業における賞与制度には以下のような特徴があります:
・年2回支給(夏・冬)が主流
・企業の業績・個人の評価に連動した金額設定
・非正規社員への支給も徐々に増加
・法律上の義務はないが、慣習として定着
・特に大手企業や製造業、金融業では賞与額が高く、年収の大きな割合を占めることもあります。
・年2回支給(夏・冬)が主流
・企業の業績・個人の評価に連動した金額設定
・非正規社員への支給も徐々に増加
・法律上の義務はないが、慣習として定着
・特に大手企業や製造業、金融業では賞与額が高く、年収の大きな割合を占めることもあります。
【比較】ヨーロッパ・アメリカとの違い
◎ ヨーロッパの賞与制度(例:ドイツ、フランス、イタリア)
ヨーロッパでは、「13か月目の給与(13th-month salary)」という制度が一般的です。これは通常の月給とは別に、年末に1か月分の給与を追加で支給するもので、多くの企業で慣例的に実施されています。
背景には以下のような事情があります:
・生活費負担の平準化
冬季の出費(クリスマス、暖房費、贈答など)がかさむことから、従業員の生活を支える目的で13か月目給与が導入されました。
・労働者保護思想の強さ
労働者の生活安定を重視する文化が根強く、法令や労働協約によって13か月目給与が義務付けられている国(イタリア、スペインなど)もあります。
・定期的かつ一律の支給
日本のように業績や評価に応じて変動するのではなく、「全社員に一律支給」「固定支給」という形が多いのも特徴です。
◎ アメリカの賞与制度
・成果報酬型のインセンティブボーナスが主流
アメリカではボーナスはあくまで「追加報酬」であり、業績や成果に応じて支給されます。
・支給頻度や金額に大きなばらつき
日本のように定期的なボーナスは一般的ではなく、特に営業職や管理職では「成果連動型の年次ボーナス」が主で、ゼロ支給の場合もあります。
・年俸制+業績ボーナスが標準
年収ベースの契約に、業績次第で数%〜数十%の報奨金が上乗せされるスタイルです。
ヨーロッパでは、「13か月目の給与(13th-month salary)」という制度が一般的です。これは通常の月給とは別に、年末に1か月分の給与を追加で支給するもので、多くの企業で慣例的に実施されています。
背景には以下のような事情があります:
・生活費負担の平準化
冬季の出費(クリスマス、暖房費、贈答など)がかさむことから、従業員の生活を支える目的で13か月目給与が導入されました。
・労働者保護思想の強さ
労働者の生活安定を重視する文化が根強く、法令や労働協約によって13か月目給与が義務付けられている国(イタリア、スペインなど)もあります。
・定期的かつ一律の支給
日本のように業績や評価に応じて変動するのではなく、「全社員に一律支給」「固定支給」という形が多いのも特徴です。
◎ アメリカの賞与制度
・成果報酬型のインセンティブボーナスが主流
アメリカではボーナスはあくまで「追加報酬」であり、業績や成果に応じて支給されます。
・支給頻度や金額に大きなばらつき
日本のように定期的なボーナスは一般的ではなく、特に営業職や管理職では「成果連動型の年次ボーナス」が主で、ゼロ支給の場合もあります。
・年俸制+業績ボーナスが標準
年収ベースの契約に、業績次第で数%〜数十%の報奨金が上乗せされるスタイルです。
おわりに
日本の賞与は、江戸時代のいわゆる盆暮れ正月の【おこづかい】が、戦後の経済成長期に制度として確立されてきた、とても特殊な制度だといえます。一方、ヨーロッパでは生活支援と安定のために「13か月目給与」が、アメリカでは成果重視の「インセンティブ型ボーナス」が根付いています。
今では常識となっている日本の賞与ですが、その歴史は意外に浅い。経済成長が鈍い日本において、賞与そのものの考え方が変革する日がくるかもしれません。
今では常識となっている日本の賞与ですが、その歴史は意外に浅い。経済成長が鈍い日本において、賞与そのものの考え方が変革する日がくるかもしれません。